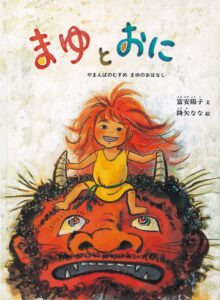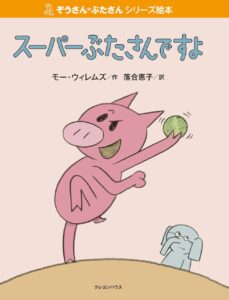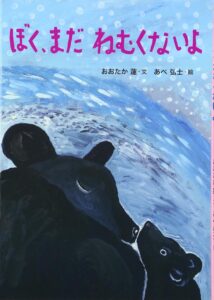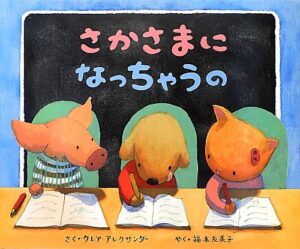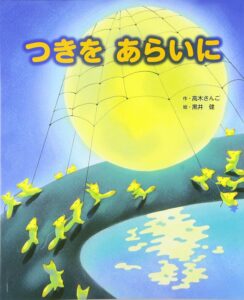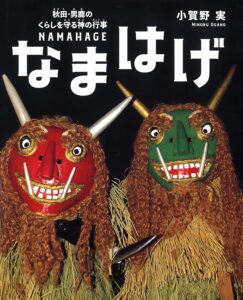こんにちは。管理人のネズミックです。
今回は、子どもと一緒に図鑑を楽しむときにふと感じた“調べもののむずかしさ”について書いてみようと思います。
外遊びや幼稚園の帰り道、歩いているといろんな虫に出会います。

「これ、なに?」「図鑑で調べてみようよ!」と盛り上がったのに、
いざ探してみると……「載ってない!?」なんてこと、ありませんか?
先日、子どもたちが集まって道ばたで見つけた小さな虫を調べたとき、
まさにそんな場面に出会いました。
今回はそのエピソードをきっかけに、
図鑑との向き合い方や、おすすめの昆虫図鑑などをご紹介していきます。
“正解を探す”だけじゃない、図鑑の楽しみ方を、いっしょに見つけてみませんか?
図鑑で調べるのって、むずかしい?
「これ、なに?」「図鑑でしらべよう!」——
子どもと一緒に虫や花を見つけたとき、まず頼りたくなるのが図鑑です。
でも実際にページをめくってみると、
「え、載ってない?」「探してる名前が出てこない……」と、思ったよりも苦戦することってありませんか?
先日、子どもたちが道ばたで見つけた小さな虫。
「ダニっぽい……?」と思ってスマホで検索してもなかなか名前がわからず、図鑑を開いても索引に“ダニ”が見当たらない。
「あれ、やっぱり載ってないのかな?」と一瞬あきらめそうになったのですが、
よーくページを見てみたら……なんと表側の目次の「クモのなかま」のところにしっかり載っていました。
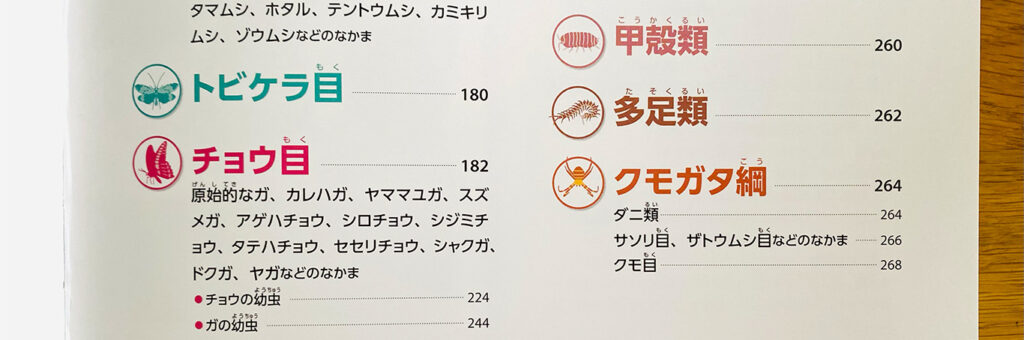
つまり、「載っていない」と感じたのは、載っていないのではなく、探し方に慣れていなかっただけだったんです。
思い返せば、これまでにもそんなことが何度もありました。
図鑑って、最初から「はいこれ!」と教えてくれる便利な本ではなくて、
自分で“あたりをつけて探す”という、ちょっとしたコツや経験がいる本なんだなと感じます。

だからこそ、子どもと一緒にあれこれ言いながら探す時間が大切。
「クモってことは、あしが多いのかな?」「同じような大きさの虫はここにいるかも」と、
“手がかり探し”そのものが図鑑の醍醐味なのかもしれません。
大人は索引、子どもは「まえのほう」「うしろのほう」
大人が図鑑を使うときって、まず索引を開いて、ページ数を確認して、
一発で「正解」にたどりつこうとしますよね。
「載ってない!」と焦ってしまうのも、たいていこの“索引まかせ”だからかもしれません。
一方で、子どもたちはまったくちがいます。
索引なんて見ないし、見たとしても「小さい字がいっぱいあるページ」という印象しかないことも。
でもそれでいいんです。
あるとき、息子が「きょうりゅうの図鑑で、トリケラトプス見せて!」と言ったので
「どこだっけ?索引で見ようか?」と提案したら、
「ううん、もっとまえのほうだったよ」「あ、ここらへん!」と、
自分の記憶と感覚でページをパラパラ。
正確な名前も知らないのに、「このへんにいた気がする」と言いながら、
好きなページをなんども開いている姿に、「図鑑って、こうやって使うんだなあ」と目からウロコでした。
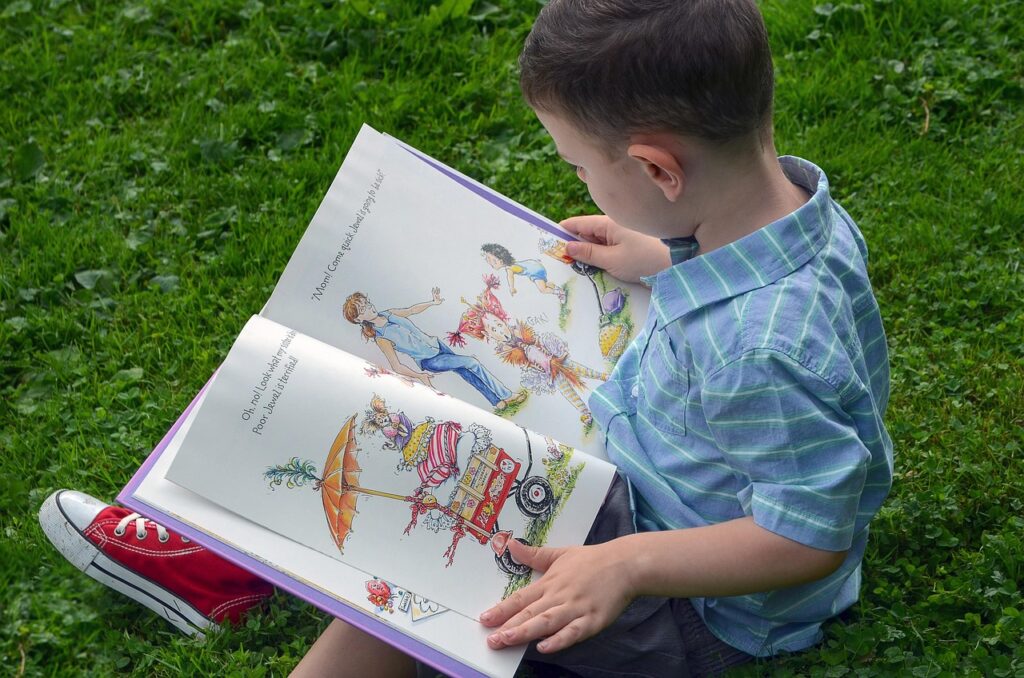
子どもにとって図鑑は、「正解を探す辞書」ではなく、
「好きなものにもう一度会いにいく本」なんですよね。
「さっきのあの赤いやつ、どこだった?」「ここにも似たのいるよ!」
ページをめくるたびに、会話がどんどん広がっていきます。
そして気づけば、いつのまにか“索引のページ”にだって自分から戻って調べるようになっていたりして。
大人が思うよりずっと、子どもは“調べ方”を自分のペースで身につけているんだなと感じます。
調べものは「正解」じゃなくて「時間」
図鑑を使って調べものをするとき、大人はつい「ちゃんと正しい答えにたどりつけるか」を重視しがちです。
でも、子どもと一緒にページをめくっていると、だんだんわかってきます。
本当に大事なのは、“答え”よりもその途中の時間なんだということに。
たとえば、見たことのない虫を見つけた日。
「これ、なに?」「図鑑で見てみよう!」と意気込んでページを開く。
なかなか見つからない、間違えて別の虫を指差す、途中で好きな虫に寄り道する……
そんなふうに行ったり来たりしながら、「これかな?」「似てるね!」と盛り上がる時間こそ、図鑑の醍醐味です。

これは、ネット検索と大きくちがうところ。
キーワードを入れれば一瞬で「正解」にたどりつくスマホとは違い、図鑑は答えにたどりつくまでの“遠回り”がむしろ楽しい。
どこに載ってるのか迷ったり、偶然ほかの虫に出会ったりするたびに、
子どもは世界の広がりを肌で感じているように思います。
図鑑を通して交わす「これ見て!」「こっちのが好き!」というやりとりは、
知識を増やすだけじゃなく、親子の距離もぐっと近づけてくれます。
だから、「見つけられなかった」なんて気にしなくていいんです。
調べているその時間こそが、いちばんの学びであり、楽しみなんですよね。
親子で楽しむおすすめの昆虫図鑑
せっかくなので、今回のような虫探しにもぴったりな図鑑を2冊ご紹介します。
学研の図鑑LIVE 新版 昆虫
日本にすむ昆虫と、クモ・ダンゴムシなどの陸上の節足動物を中心に、約2800種を掲載した本格派の図鑑。すごいのは、すべての昆虫を生きたまま白背景で撮影しているというところ。子どもが実際に虫を見つけたときと近い印象で載っているので、「これだ!」と見つけやすいのがポイントです。
じぶんでよめる こんちゅうずかん(成美堂出版)
まだ字が読めない、図鑑に慣れていない子にもやさしい、図鑑デビューにぴったりの一冊。今回の“ダニ”のようなマニアックな虫は載っていませんが、ひらがなでやさしく書かれていて、「自分で読めた!」という達成感を味わえるつくりです。
図鑑は「ひらく」ことからはじまる
索引から調べるのも、もちろん大事。でも、子どもたちが自由にページをめくって、「これみたことある!」「これ、さっきの虫!」と盛り上がっている姿を見ていると、図鑑って、“ひらくこと”そのものがもう楽しいんだなと感じます。
「調べる」ことは、「話す」「聞く」「見つける」ことでもある。そんな風に思える時間を、これからも子どもと一緒に楽しんでいきたいなと思います。